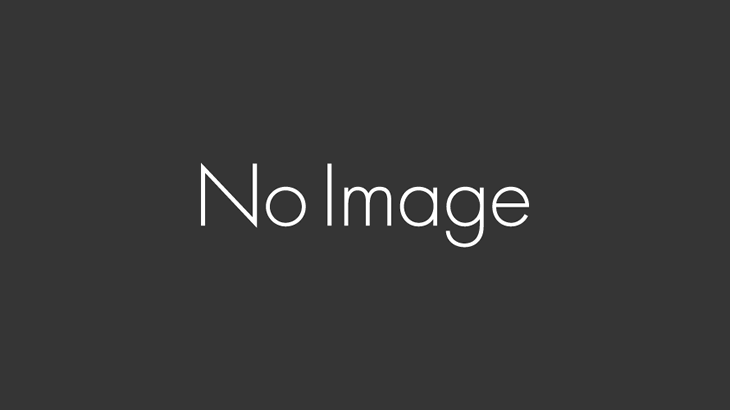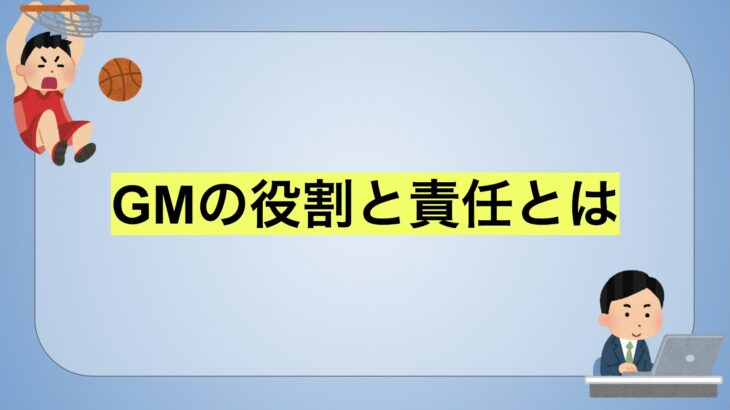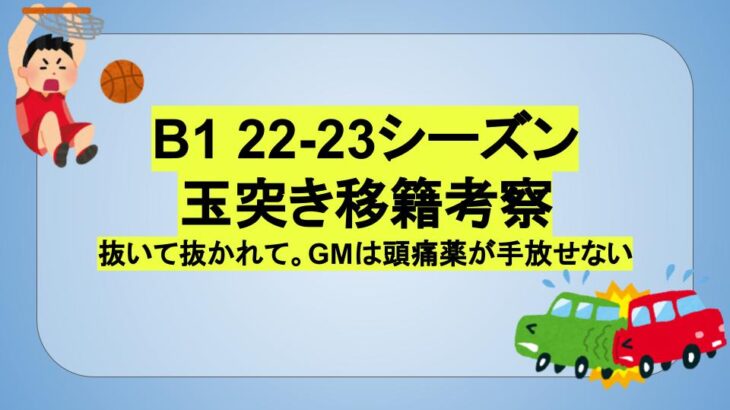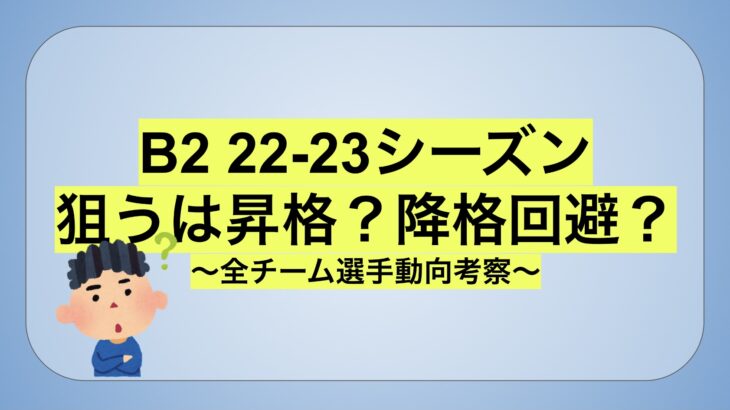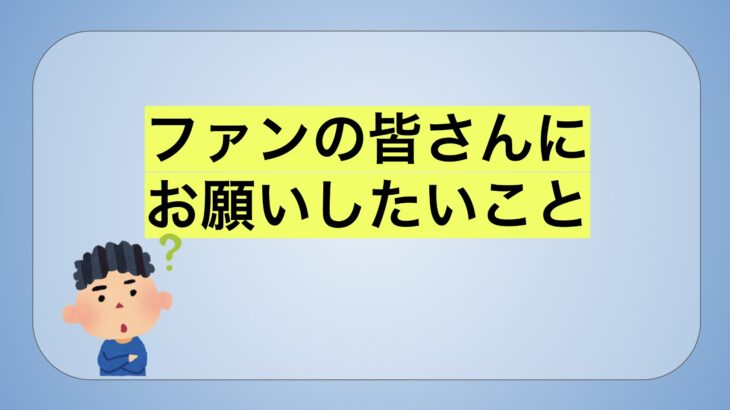この記事は約7分で読めます。
きのう、こんなツイートを見つけた。
面白かったので、私の考察を書いていきたいと思う。
主な内容
元ネタの内容が出た主な流れはこうだ。
Bリーグで日本人ビッグマンのプレイタイムが少ない。代表強化の視点から見るとリーグでもっと成長してほしい
↓
ビッグマンはポジションとしても重要で、かつ外国籍との能力差が大きいから、外国籍を置くことが多い
↓
それなら日本人ビッグマンを置いて、ガードを外国籍にして優位性を創ったら面白いチームになるのでは?
という感じだったと思う。(違ったらごめんなさい。この流れもどこかの話にはあったはず…)
そしてこれは私は面白いし、実際やってもそこそこ結果を残せるラインナップになると思っている。
(細かいベンチユニットとかの話は一旦割愛する)
元ツイの方は、外国籍ビックマンは上位チームが契約して下位チームは契約が難しいから、ポジションが違うガードの優秀な外国籍を獲ることでこのような面白く、日本人ビッグマンにプレイタイムを与え、かつ可能性があるチームを創れると考えたらしい。
下位チームが下位なのは別の理由だと思っているのだが本筋からそれるので割愛する。
今回書きたいのは、なぜ「外国籍ガード&日本人ビッグマン」のラインナップが存在しないか。である
考えられる主な原因
・日本人ビッグマンの能力不足と悪しき伝統
1つ目の存在しない原因は、純粋に日本人ビッグマンがコーチの信頼を勝ち得るだけの能力がないことだ。NBAで活躍する八村塁、渡邉雄太がいい例だが、国籍が日本でも外国籍といわれるアメリカやヨーロッパの選手とは渡り合うことが出来る。
にもかかわらず、Bリーグで日本人ビッグマンが外国籍の控えとしてベンチを温め、プレイタイムが少ないのは、純粋に能力不足の可能性が高い。能力不足の原因は沢山ある。
・学生時代から留学生に活躍の機会を奪われている
・日本では195㎝程度からビッグマンと呼ばれるが海外のビッグマンは205cmを超える為身長のディスアドバンテージを背負うため
・外国籍選手と渡り合うフィジカル、スキルを身に着ける経験が国内で得にくい
など、日本バスケの育成の仕組みの問題から始まる根深い原因がある。
また、日本バスケはBリーグ統合前から長年外国籍選手をインサイドに置き、日本人選手をアウトサイドに置くスタイルがトップリーグから主流だったことも日本人ビッグマンが外国籍選手と比較して起用されづらい原因かもしれない。要は「インサイドは外国籍の屈強な選手を置くもの」という半ば固定概念が出来ている。
・チャレンジするコーチのメリットが少ない
2つ目の原因は、インサイドに日本人ビッグマン、アウトサイドに外国籍選手を配置するラインナップをやるメリットがコーチにあまりにも少なくリスクの高いことであることだ。
前述した通り、日本バスケは長年外国籍ビックマンをインサイドに置くラインナップを主体としたバスケットボール文化が続いている。
その日本において外国籍ビックマンをロスターに含めない、含めても控えにするという判断は、これまでの培った実績や経験から反するチャレンジになる。心理的に抵抗があり、定石として外国籍ビックマンを配置する安心感を捨ててまで選ぶのは大変勇気のいる決断だと思う。
また、その決断をしたとして結果が伴わなければ、チームを率いて勝利を求められる「コーチ」としての役割を果たすことが出来ないと判断されかねない。そして決断は当人のキャリアに跳ね返ってくる。
球団の理解を得ることも相応に大変だが、理解を得て編成できたとしてもリスクが高いと感じるコーチが多くてもやむ負えないだろう。
つまり、日本バスケ界にとっては結果問わず賞賛すべきチャレンジだが、そのリスクは現状ではコーチ個人が負う形になっているわけだ。そんな分の悪いギャンブルしたくないのは当たり前だ。
・「勝つ」のなら不要な選択である
3つ目の原因は、コーチが求められる「勝利」を求めるなら、そもそもそんな新しいラインナップに挑戦する必要が無い。仮に新しいラインナップでリーグ戦に挑み、そこそこの成績を残したとして、外国籍に関わるルールが変わらない限り、外国籍ビックマンを擁した時とどっちが良いかは比較される。
そして、長年外国籍ビックマンに慣れた日本ではバイアス(思い込み)も含めて外国籍ビックマンがいるラインナップを評価する可能性が高い。
チャレンジして、結果を出してなお認められない可能性があるのなら、定石を積み上げる方が勝利を考えた時にはよほど安全である。
代表強化とリーグの発展が相反している現状
冒頭の記事のきっかけになった話の流れで書いた通り、日本代表強化の視点で行くと、現在の「日本人ビッグマンプレイタイムが少ない問題」については解消されなければならない。
プレイタイムにこだわらなくてもよいが、国内選手が代表戦で海外代表(=外国籍)にタメ張って戦えるようにならないといけないのだ。その為に国内リーグで競争に勝って実戦の経験を積み、成長するのが今後の継続的な強化も視野に入れると必要になってくるのだ。
国内リーグでプレイタイムを確保するアイデアは沢山出てきている
・韓国を参考に外国籍の身長制限を設ける
・ベンチの登録人数やオンザコート数(コート上に同時に立てる外国籍人数)を変化させて日本人ビッグマンが出れるレギュレーションにする
・外国籍を撤廃する
などなど、どれも一長一短あるが多種多様だ。
同時にそもそも「外国籍に勝てない日本人ビッグマンの実力不足」という声もある。意外とファンは厳しいらしい。(個人的にはこれは半分正しくて、半分間違っていると思うので言葉を濁しておきたい…)
このように問題意識はあるが現状、Bリーグは外国籍のルールなどを変える、ビッグマンをはじめとした日本人選手育成のための行動は見られない。依然、日本人ビッグマンはプレイタイムを得て成長するのは難しい状態が続くと思われる。
Bリーグもリーグの役割の一つに「日本代表強化」を掲げている以上、何かしらしてほしいとは思うが、
どこまで議論が行われているのかも含め全く表から見えないので、そとからは眺め待つことしかできない。残念な限りだ。
今回は面白いツイートがあったのでそれを基にした考えを書いてみました。
「正しいか」より、「こういう要素があるよね」という視点の共有をすることでまた誰かがその解決策を思いつくといいなと思います。
おまけ:私が考えるビッグマン強化アイデア
最後に私の考えたBリーグでの日本人ビッグマンの強化アイデアを書いてみる。
私が考えたのは、オンザコートルールの変更である。オンザコートを以下のようにする
ホーム側は1-0-2-0
アウェイは0-1-2-0
コンセプトは「勝負強いビッグマンの育成」
前半はピリオドごとに外国籍を入れ違いに制限することで「日本人ビッグマンvs外国籍ビッグマン」を両チーム10分ずつ強制的に発生させる。当然ビッグマンが2人いる場合は、日本人同士の戦いもあるが、外国籍とのマッチアップを0にするのは難しくなり、ハードな成長機会が生まれる
後半は3ピリオドをon2でそのチームの最大限のパフォーマンスを出してもらう。
外国籍のプレイタイムも計30分になるので土日の連戦を通じてうまくシェアするなどで活躍機会を確保できる。
そして4ピリオド。on0で日本人だけで戦ってもらい、インサイドをはじめとして、日本人に勝利の責任を感じてもらう。
個人的には日本人は日本バスケの風習と戦略上、勝負所は外国籍にボールを託してサポートするのが癖になっており、メンタル的に勝負所で勝負をするシチュエーションを得にくいのではないかと思っている。(一部の代表クラスを除く)
なので自分の手で勝利をもぎ取る、自分のせいで負ける実感を経験してもらい、勝利への執念を培ってほしい。
外国籍とはフィジカルとスキルの差は確かにあれど、プレイタイムを得れないほどの差があるとは感じていない。問題があるすればメンタリティだと考えてこのようレギュレーションがいいと思っている。
これなら、日本人ビックマンの強化と外国籍出場による興行的にな強度の強さを両立できるし、ファウルトラブルなどで日本人ビッグマンは飛躍的に出場機会が増える状態を創ることができると思う。
以上、今回はここまで。