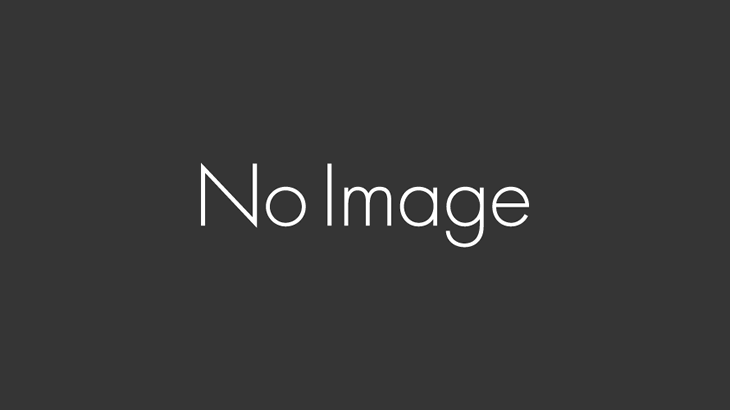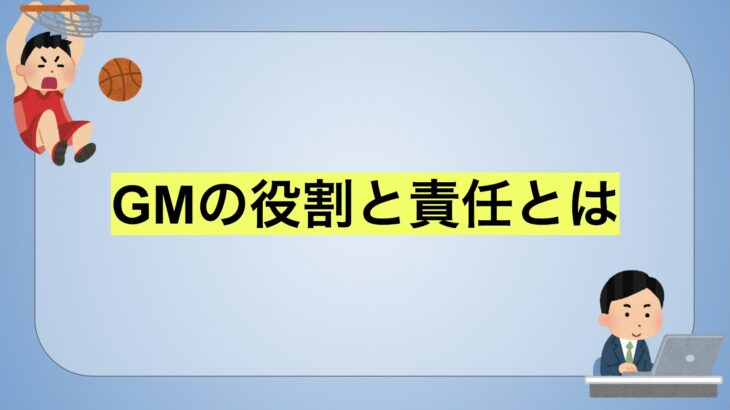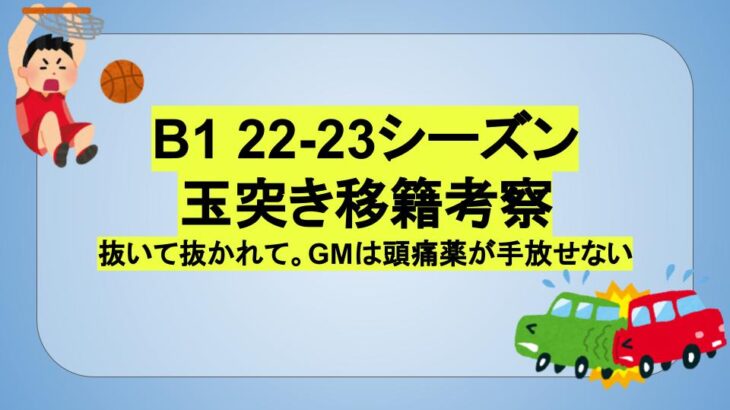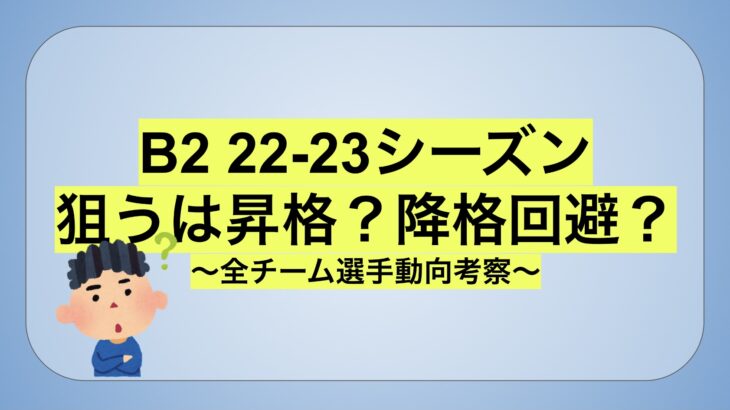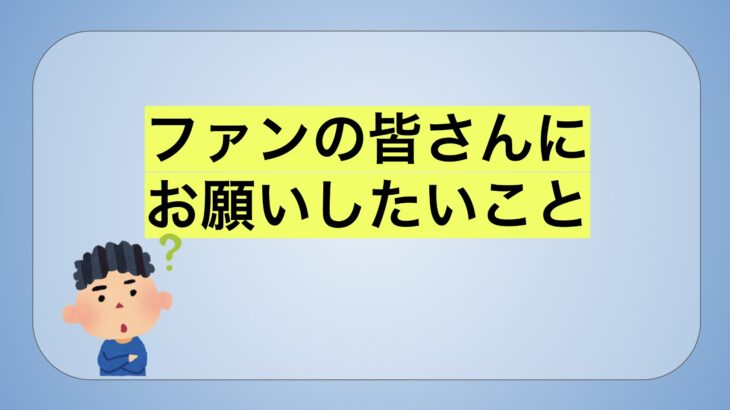この記事は約11分で読めます。
Bリーグ6年目の2021-22シーズンが宇都宮ブレックスの優勝で終わった2022年5月29日
その翌月の6月に
アルバルク東京のルカ・パヴィチェヴィッチHC
宇都宮ブレックスの安斎竜三HC
千葉ジェッツふなばしの大野篤史HC
が所属チームの退団を公表した。
理由はそれぞれ異なるが、Bリーグ創設以来優勝を経験したこの3チームのHCが揃って退団するのは、
Bリーグの1つの時代が終わることを象徴しているように感じたので、書き留めておきたいと思う。
Bリーグが2016年9月に開幕した以来、21-22シーズンまでの6年間で優勝したのは、
この3チームのみであり、その全てでこの3人のいずれかがチャンピオンチームに所属している。
まさしくBリーグをけん引したコーチたちと評するにふさわしいコーチたちだと感じている。
リーグ創設してからの、この6年は創設黎明期ともいえるような問題やレギュレーションの変更から
世界的に猛威を振るっているコロナ禍など様々なことがあった。
その中で安定して、所属する東地区において上位を維持し続けたコーチングとチームビルディング能力は、間違いなくBリーグの興行的な成長と、競技力の成長の基礎を築いたといえるだろう。
彼らと所属チームが無ければ、ここまでのリーグと、代表をはじめとした
日本バスケの競技力の急成長は実現し得なかった。
彼らがいなければ、野球・サッカーという国内スポーツ産業の二大巨頭がすでに存在する日本では、
バスケ業界規模の伸び悩みや、長期的にジリ貧の状態でコロナ禍迎えて、
経営破綻したチームが出てくる未来もあり得ただろう。
そういう意味では、彼らに対しては感謝しかない。ありがとうございました。
別に引退するわけでもないので、来季もどこかのチームでコーチをしていたり、存在感を示すとは思うが、せっかくの機会なので彼らへの書いていこうと思う。
アルバルク東京のルカ・パヴィチェヴィッチHC
17-18~21-22シーズンの5シーズンチームを率いた。
HC就任初年度からリーグ二連覇を成し遂げ、その後は3シーズンコロナ禍で王者アルバルクを強豪の位置に維持しつづけた。
最後2シーズンは外国籍をはじめとする主力のケガや、
強さの源泉である練習をコロナで奪われたこともあり、
チャンピオンシップへの進出を逃した。
本来は18-19シーズンまでの3シーズンで契約満了の予定が、
コロナで伸び22-23シーズンまでの計6シーズンHCを務める予定であった。
しかし、チャンピオンシップ出場を2年連続で逃した責任を取るということで
21-22シーズンを最後として退団を申し出た。
個人的には就任初年度の17-18シーズンに見られた
ベンチでのボディランゲージとテクニカルの多さが印象的だった。
余りにも多くテクニカルファウルを吹かれていたので、
その圧倒的なコーチング能力も踏まえて「ルカのテクニカルは税金」とひそかに呼んでいた
※2代目「高額納税者」は滋賀レイクスターズのルイス・ギルHCである。
特に彼の指導力の凄さを感じたのは、
田中大貴選手(A東京)のポイントガードへのコンバートと、若手の戦力化の早さである。
田中大貴選手は元々SG/SFのポジションであったが、
当時の日本代表の選手の大型化のコンセプトを受け、
代表ではポイントガードとしてコンバートし、ゲームコントロールと時にはスコアリングを担う、
日本トップのユーティリティプレイヤーになった。
本来プロになってからのポジションの変更は、
プレイスタイルやコート内での役割、求められるスキルなどもあり、あまり行われない。
ましてコート内の司令塔と呼ばれるポイントガードは、特にコンバートが難しいポジションである。
爆発的に考えることが増え、オフェンスの始動を担うため、
最も激しいプレッシャーを受けながら最も間違えない判断と行動をとらなければならないからである。
要は、代表の時だけポジションを変えるなんていうその場しのぎで何とかなるポジションではない。
ましてや代表クラスではなおさらである。
その為、リーグ戦中でもその役割の経験を積んでいく必要があるのだが、
田中大貴選手は、見ている限りだと圧倒的な速さでコンバートを成し遂げたように見えた。
本人のポテンシャルの高さは元々日本トップクラスではあるが、
意識の変化だけでできるものでもない。
圧倒的な速さの裏には、ルカHCを始めとしたコーチ陣のサポートがあったように感じられた。
実際19-20シーズン辺りからは正ポイントガードがコートにいないときに、
田中選手がゲームコントロールする場面が増え、それはシーズンを経るごとに長く、安定感が増した。
チームとしてもオフェンスの起点が複数できることは、オフェンス力の強化にもつながり、
より一層アルバルク東京というチームを成長させた。
2つ目の若手の戦力化の早さについては、特に21-22シーズンでチームの危機を支えた
小酒部選手、吉井選手、平岩選手がオンコートで活躍している場面を見て感じた。
アルバルク東京でプロデビューする選手は総じてポテンシャルが高いが、
そのポテンシャルを1年強の短い期間でプロ仕様に仕立て上げ、
オフェンスとディフェンス両面でリーグトップクラスの基準まで持ってきた。
例年どのチームであっても、ルーキーや二年目はプロの強度のアジャストに苦労し、
攻守のムラなど経験の浅さや、フィジカル負けすることが多くみられる。
それがほぼなく、リーグ終盤、チャンピオンシップで外国籍・帰化選手の穴を埋めて、
勝利に貢献したことは、間違いなくルカHCのメソッドによるものであるといえるだろう。
ぜひリーグ全体に配布したい。
ファンからもルカの顔をイラストした「ルカフラッグ」が作られるほど愛された。
個人的には欲しかった。。。
試合後のインタビューでは日本語でのあいさつなども積極的に行い、
ファンも含めてアルバルクの文化を作っていった。
心なしかだが、16-17シーズンに比べてアルバルクのファンの方の雰囲気が良い方向で変わっていったことにも影響していると感じている。
宇都宮ブレックスの安斎竜三HC
16-17シーズンはACとしてBリーグ初年度優勝を経験、
その翌シーズンの途中から21-22シーズンまで5シーズンHCを務める。
21-22シーズンはHCとしてBリーグ優勝を成し遂げた。
BREXNATIONと呼ばれる熱狂的なファンと長年宇都宮ブレックスに在籍している
田臥選手、渡邊選手、遠藤選手、竹内公輔選手などと
共に圧倒的な守備力と粘り強さでチャンピオンシップにフル出場した。(19-20はコロナの影響で中止)
19-20シーズンからはライバルのシーホース三河のエースで日本代表の比江島選手を迎え入れ、
チームの進化に挑戦した。
20-21シーズン終了後にそれまで5シーズン以上在籍した
ライアンロシター選手(現A東京・帰化選手)、ジェフ・ギブス選手(現B2長崎・外国籍)が移籍し、
大幅なチームの転換期を迎えたが、前述した比江島選手を中心としたチームを完成させ、
優勝を果たし、退団した。
個人的には、アルバルク同様若手や移籍組の戦力化が早いことと、
選手への信頼が伝わるしぐさが印象的である。
宇都宮ブレックスはファンの熱狂具合や、長年在籍しているベテラン選手のリーダーシップも強く、
それがブレックスメンタリティを生み、入団したての選手の成長を促す。
竜三HCはその成長を見守りつつ、プレイタイムを与えてどの選手が出場しても
コート内の強度が落ちない、「THE・チーム」とも呼べるケミストリーを構築している。
特に21-22シーズンは帰化選手が途中で契約解除しチャンピオンシップでは、対戦チームすべてに帰化選手が存在する中で、田臥選手を除き、出場選手全員に20~25分前後のタイムシェアをしつつ6連勝して優勝した。
例年、強豪チームがせめぎ合い、短期決戦のチャンピオンシップでは主力が28~35分程度出場して
強度を保つため、プレイタイムはレギュラーシーズンより偏りやすい。
そんな中、得点が競っている状態でも選手をローテーションして出場させた。
当然競っているためベンチメンバーが出場して点差を詰められることなどもあり、
以前はタイムアウトや主力をすぐ戻して対応するシーンが見られたが、
今シーズンではそのような対応は少なく、選手を見守った。選手はその期待に応えて、
点差を詰められつつも崩れずに安定感をもってゲームを進める信頼関係を感じられた。
(追記しておくが、強豪との短期決戦では少しのミスで優位性がひっくり返るため
信頼の有無に関わらず選手を交代する判断を取ることが多い。
決して交代が信頼が無いということではないということだけ留意していただきたい)
今振り返れば以前見られた檄を飛ばしたり、作戦盤をたたきつけるほどの怒りや迫力が少なくなり、やわらかい表情が増えたのは退団を決意していたからなのかもしれないとふと思った。
千葉ジェッツふなばしの大野篤史HC
Bリーグ初年度から千葉ジェッツのHCに就任し、
チームコンセプトの「アグレッシブなディフェンスから走る」スタイルを体現。
全シーズンチャンピオンシップ出場、20-21シーズン優勝、天皇杯3連覇を達成した。
個人的にはベンチでは檄をとばすというより、諭すようなコミュニケーションを多く取っている印象。
「なぜ自分たちが試合をするのか、誰の為に試合をするのか」など、
選手の人間性も育てるコーチングするのが印象的だ。
その影響もあってか、千葉では選手がファンサービスや広報に積極的で
それが観客動員TOPなどの記録に繋がる好循環を生み出しているのかもしれない。
強力なリーダーシップでまとめ上げるスタイルでない分、
選手の波があったり、初年度では選手の仲間割れがコート内で起こるなど、
不安定さが見られることもあったが、その分ハマると手が付けられないチームへ変貌する。
選手を信頼し主体性を尊重しつつ、導くタイプのコーチングをすることで、
選手も信頼を感じ取り、自身の役割を理解してチームに貢献するようなる。
主体性とマインドも成長し、プレイタイムの偏りが発生しても納得して受け入れ、
限られたプレイタイムに抜群の仕事をする選手に育つ。
チームコンセプトに沿ったチームビルディングを徹底して結果を出す手腕や、
試合後のインタビューや取材の様子を見ると、
競技コーチではなく、メンタルコーチングに寄っているコーチングスタイル・性格の為、
コーチへのコーチングやアンダーカテゴリーへのコーチングなど、
クラブの文化をコートに体現して作っていくコーチになっていくのだと思う。
振り返ると富樫勇樹選手というスペシャルかつピーキーな選手を活かせているのは、
選手本人の実力もあるものの、選手への信頼があってこその活躍っぷりであるのだと感じた。
次のチームでも選手を育てて愛されるチームをコートから作り出していってほしい。
チームの文化は選手とコーチとファンが作る
コーチの退団はこれまでも各チームであったが、その中でも今回の3名の退団に時代の終わりを感じたのは、チームの文化にコーチが寄与していると感じたからだ。
当然年数だけではないが、やはり長年同じチームにいる人物のマインドや姿勢は
クラブに影響を与える。
結果論かもしれないが、在籍が長いコーチや選手が複数人いるチームの成績は安定している。
それだけにこの5~6年Bリーグをけん引したチームを率いた3名は
そのまま3球団の文化、そしてBリーグの文化の礎を築いたと思うからだ。
アルバルク東京は、強いものの熱烈なファンは少ないイメージから熱烈なファンが生まれ、クラブの看板以外にもファンの為にも負けられないといういい意味のプライドを感じるようになった
宇都宮ブレックスは、元から熱烈だったファンがより熱狂的になり、栃木どころかアウェイのアリーナでも黄色く染めるBREXNATIONを作り上げた。
千葉ジェッツふなばしは、Bリーグ開幕後は最高勝率や天皇杯3連覇、観客動員1位などの目に見えるファンとの共創を体現した。
それぞれ文化は違うものの「あのチームと言ったらあれだよね」といわれるものを持っている。
その文化は今回退任したコーチが選手とファンと共に創り、
この後はファンと選手が引き継いで守っていくのだと思う。
同じ形で選手やファンも文化を創っている。
可能であれば作り上げた文化を各チームの色、ひいては強みとして残していき、
チームの資産としてほしい。
「あなたの応援はちからになる」よく使われるが、
文化があるチームを応援しているかたにはこの言葉の重みが分かるだろう。
文字通り、ちからになるのだ。文化を歴史を創り、それがぶれない強さを生み出す。